伝統芸能《志賀団七踊り》
志賀団七踊り(西時津郷)
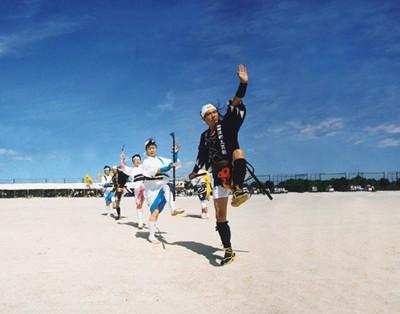
1. 由来
むかし、宮城野、忍という姉妹と、その父が田の草を取り、道の脇へ上げたところ、そこを通りかかった武士の袴の裾を汚してしまいました。
武士が怒ったので、父が子どものしたことであるのでと、何度も謝ったが、聞き入れられず、子どもの目前で手打ちになってしまいました。
そこで、姉妹は、父の仇を討つため、武術の修行を積み、仇討ちをしました。その場面を表しているのが「志賀団七」であるといわれています。
2. 行列の構成
イ 踊子 女大多数
ロ 山 三味線 1人 太鼓 1人
ハ 忍 1人
ニ 志賀団七 1人
ホ 宮城野 1人
ヘ 人数 忍、志賀団七、宮城野の3人組で何組でもつくるので、人数は不定。
3. 芸能の構成
イ 道行き
平作囃子を三味線と太鼓で演じ踊子が先頭に立ち行進する。
ロ 本踊り(忍、志賀団七、宮城野の踊り)
平作囃子と同じ曲であるが、ややテンポを早くした曲を演じ、三人のからみの演技が始まる。
ハ 掛声
道行き、本踊りの時も、調子に合わせて、エイヤ、エイヤ、オーの掛声が入る。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
社会教育課 社会教育係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3978(直通)
ファックス番号:095-881-2725



更新日:2019年03月01日